2024年度土木学会全国大会 International Program (国際関連行事) のご案内
国際センターでは全国大会開催期間中(9月4日(水)~6日(金))に以下の行事を実施致します。
土木技術者、研究者、学生の幅広いご参加をお待ちしております。
★各行事の詳細について、今後本HPにて情報を更新致します★
【お知らせ】
・ウェブサイトをオープンしました(2024/7/4)
1. 国際関連特別講演会「土木の分岐点@ジャンクション、みち、未来 ~パラダイムシフト~ 」
・言 語:講演会での言語は日本語が主です。※日本語→英語の同時通訳を導入します。
・司会進行:岩井 裕正准教授(京都大学)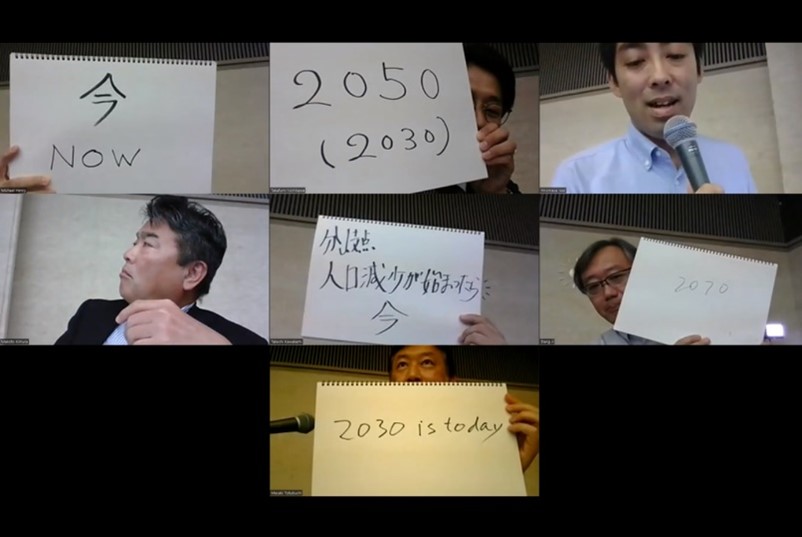
◆プログラム:
日本の土木界が抱える様々な課題に対して,土木学会は,それらの中で何をいつまでにどのように取組み,成し遂げるべきなのか,
そして土木技術者の役割と責任を明確にし,具体的な行動にする。
1.開会&趣旨概要(5~7分)
・開会挨拶:国際センター長 木村 亮
・趣旨と前回の議論のポイント紹介:司会・モデレーター 岩井 裕正 准教授(京都大学)
2.基調講演(1名:40~45分名)
・中村 幸司氏(日本放送協会)
3.ディスカッション (60~65分) 4名
・登壇者:木村センター長、徳渕 正毅氏(ARUP)、中村幸 司氏、松永昭 吾氏(インフラ・ラボ)
◆お申込み:
・対面参加:https://soumu.jsce.or.jp/subs20240904/start.html
(オンライン参加の方)
→下記URLよりオンライン参加をお願いいたします。
なお、本ウェビナー定員は500名です。アクセス多数の場合、入室できない場合もございます。お含みおきをお願いいたします。
※CPD受講証明書の発行を希望される方は、ウェブサイト「【https://committees.jsce.or.jp/zenkoku/R6CPD/」にアクセスし、事前にお申し込みをお済ませください。
-----------------------------
・Zoom URL:https://zoom.us/j/99008429604?pwd=2ctO2r9dAfKDxsdZc7rAO9SHQwdgo0.1
ID: 990 0842 9604
パスコード:208442
-----------------------------
◆CPD:
本講演会はCPD認定プログラム申請予定です。
・認定番号:JSCE24-0802
・単位数:2.0単位
・ご注意:
現地参加の方:参加登録を行っていただいた方のうち、当日会場でQR コードによる受付を完了した方に発行します。
オンライン参加の方:CPD受講証明書を希望される方は 9/4(水)10:00 迄に参加登録を済ませてください。
【その他】
2. 第26回インターナショナルサマーシンポジウム
インターナショナルサマーシンポジウム(サマーシンポジウム)では第79回年次学術講演会(国際セッション)での「グローバルシビルエンジニアワークショップ」、「論文発表」を二部構成として、以下の日程で開催致します。
本シンポジウムは、日本国内で学ぶ留学生、若手技術者・研究者を対象に英語による研究発表、および国、研究分野を越えた交流と協働、ネットワーク形成を目的としており、毎年土木学会全国大会にて、開催しております。
なお、サマーシンポジウム、ワークショップ参加者の交流を目的としたIAC ネットワーキングレセプションを開催します。
●グローバルシビルエンジニアワークショップ(Workshop for Global Civil Engineers)
・日にち:2024年9月4日(水)
・時間(予定):14時30分~18時00分(To be updated)
・会場:仙台国際センター 桜2
・テーマ:"The Role of Civil Engineering in Achieving the SDGs” 「土木技術者が知るべきSDGs とは」
※ワークショップの一般聴講は出来かねます。
●論文発表(第79回年次学術講演会 「国際セッション(International Session)」として開催)
・日にち:2024年9月5日(木)、6日(金)
・時間:5日:終日(9時00分~17時40分)、6日:9時00分~17時40分
・会場:東北大学 川内南キャンパス 文科系総合講義棟 第1講義室(法学部)
※5日 9:00~10:20は、文科系総合講義棟 第2講義室(法学部)にてパラレルのセッション開催。
セッション詳細:https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jsce2024/sessions/program/ILHTDX
※セッション聴講は年次学術講演聴講登録(https://committees.jsce.or.jp/zenkoku/gaiyo/houhou_choukou)が必要です。
●IAC ネットワーキングレセプション(IAC Networking Reception)
・日にち:2024年9月5日(木)
・時間:18時30分~19時30分
・会場:東北大学 キッチンクルール
・参加費: 無料
※要事前申し込み
★【参加申込】グローバルシビルエンジニアワークショップ、IAC ネットワーキングレセプション
https://forms.gle/b4eW5P57UmeofV2b8
※備考:
・申し込み期限:8月26日(月)まで
・日本人学生、技術者の皆様の参加を歓迎します。
◆お問い合わせ:
(公社)土木学会 国際センター
Tel: 03-3355-3452
Email: iad@jsce.or.jp